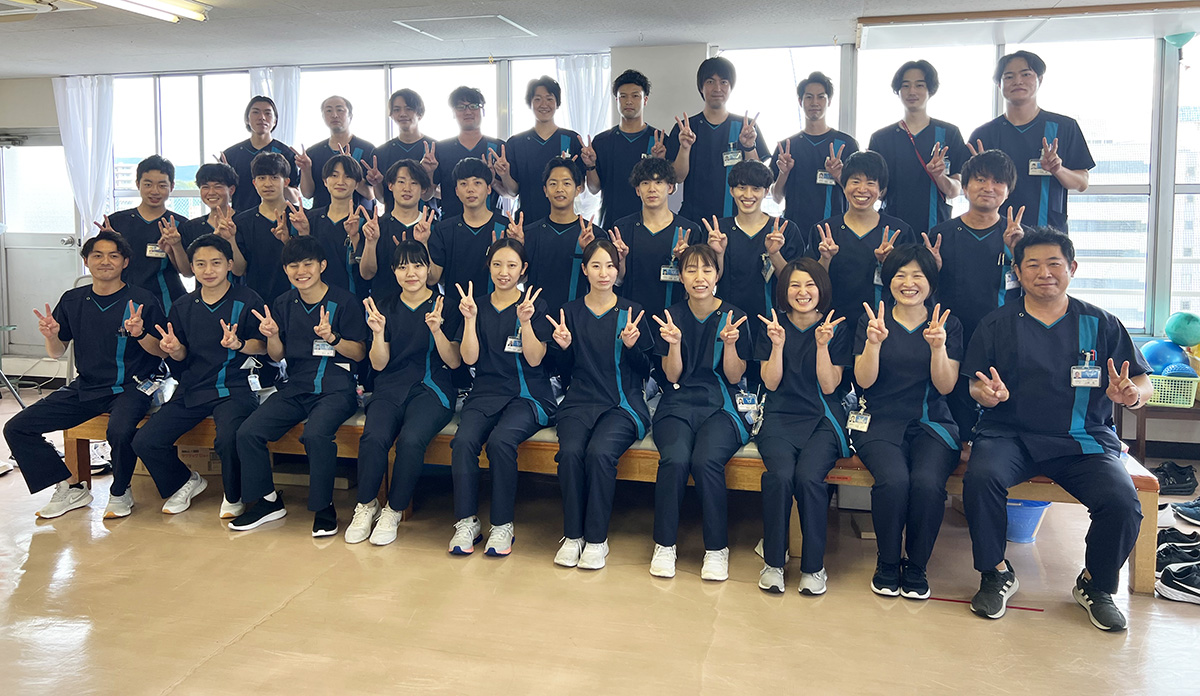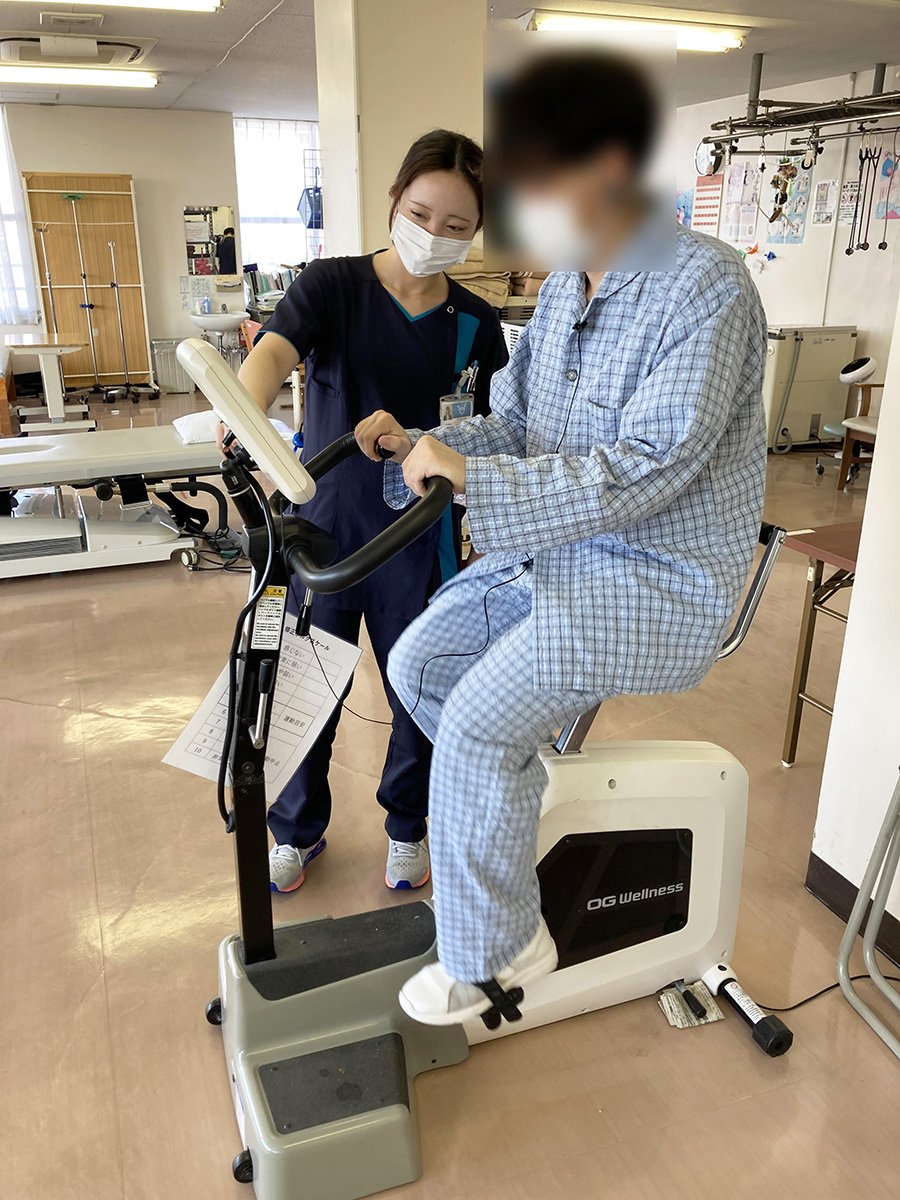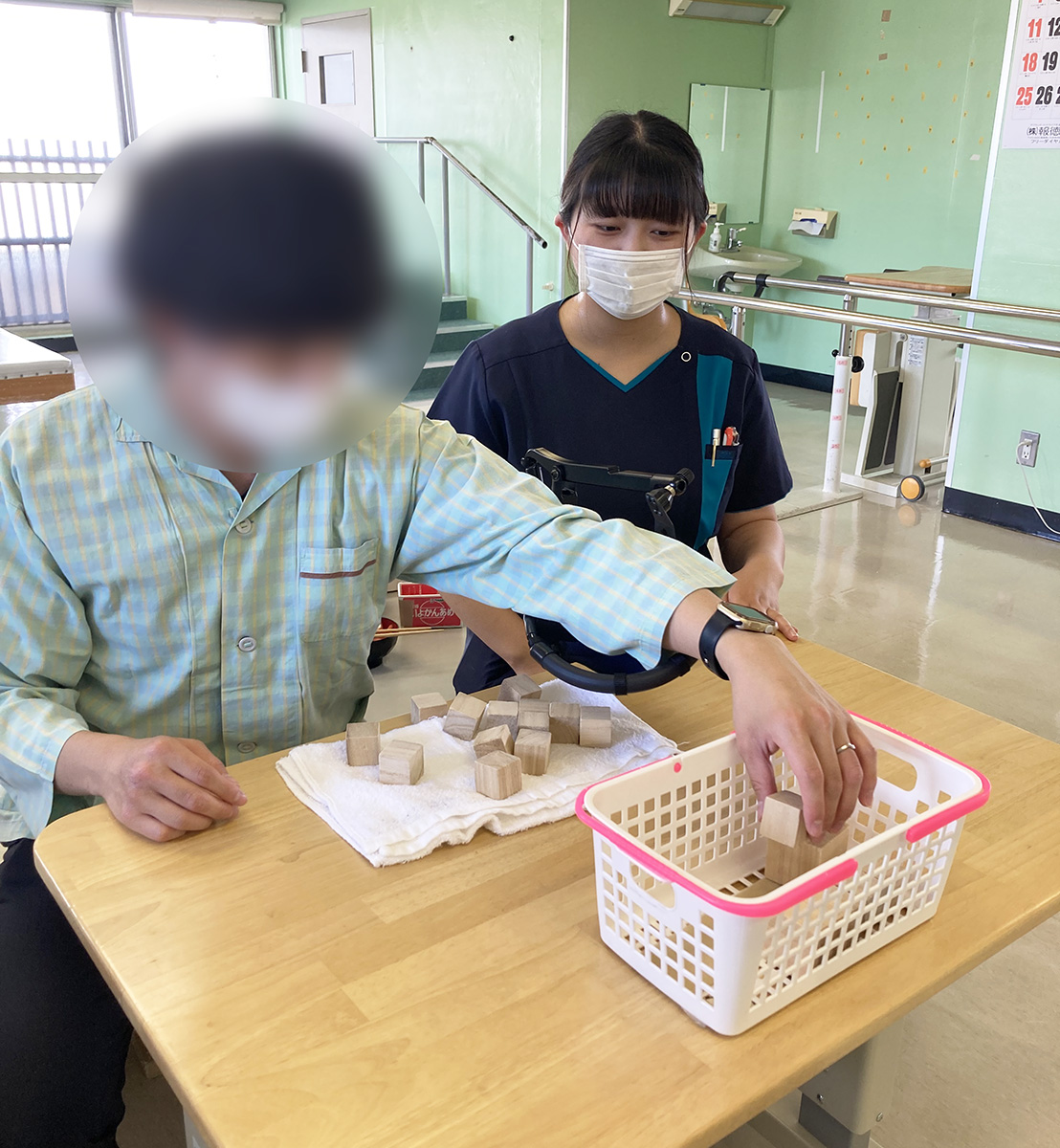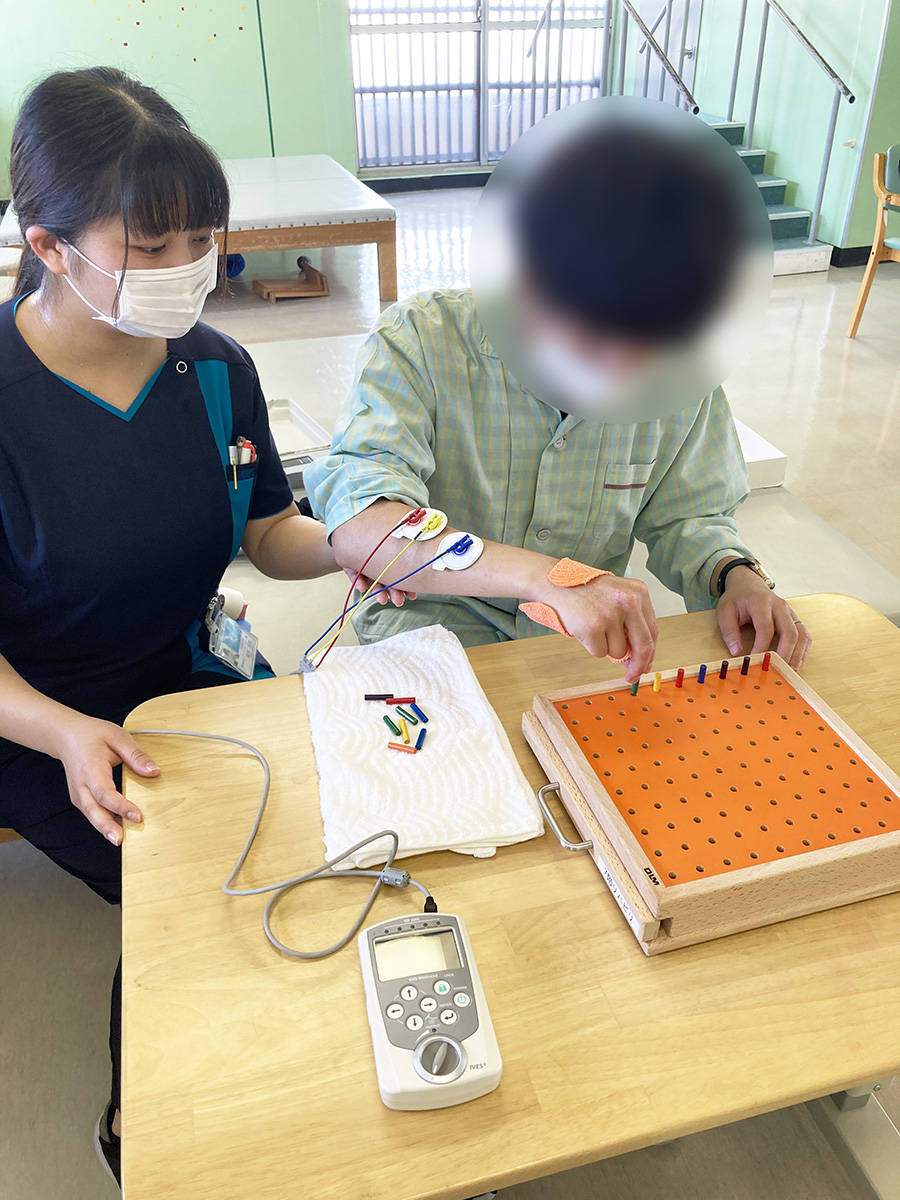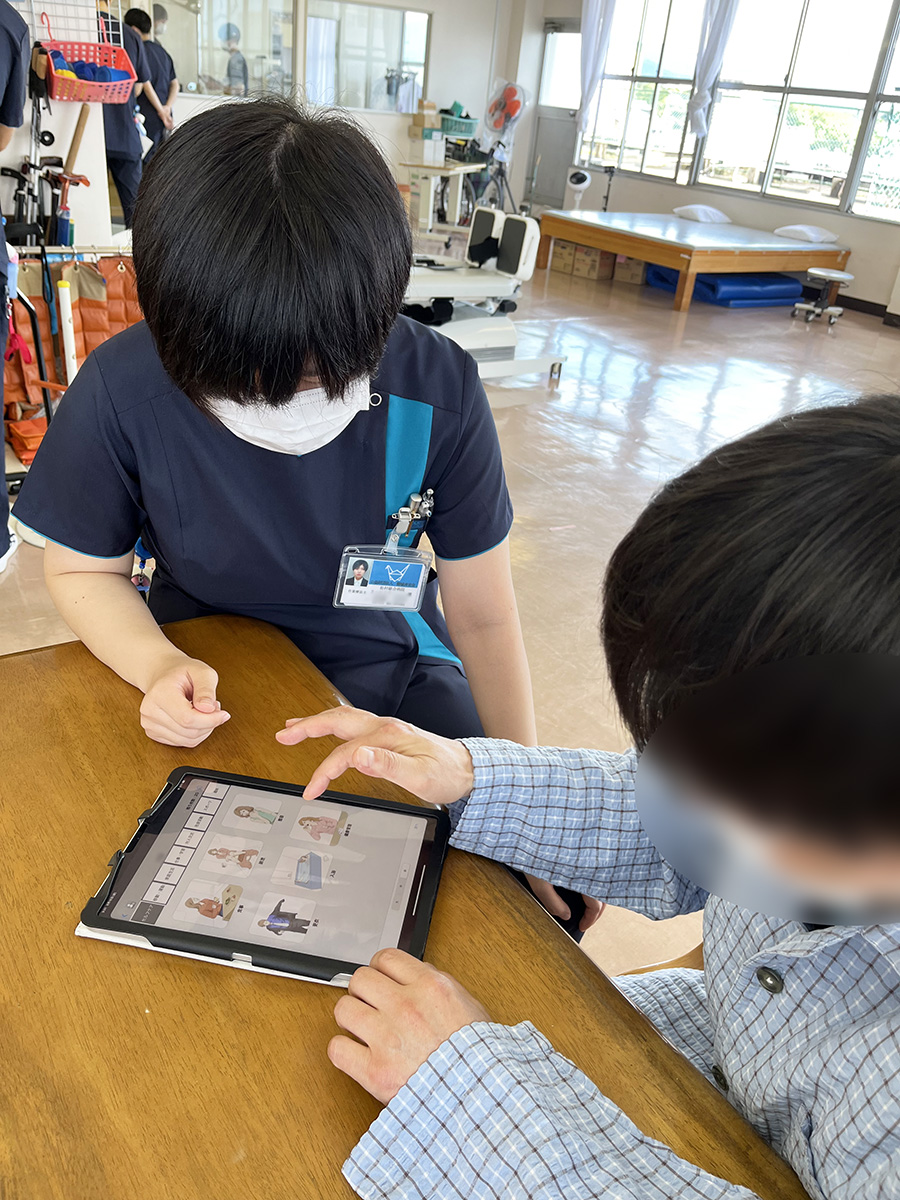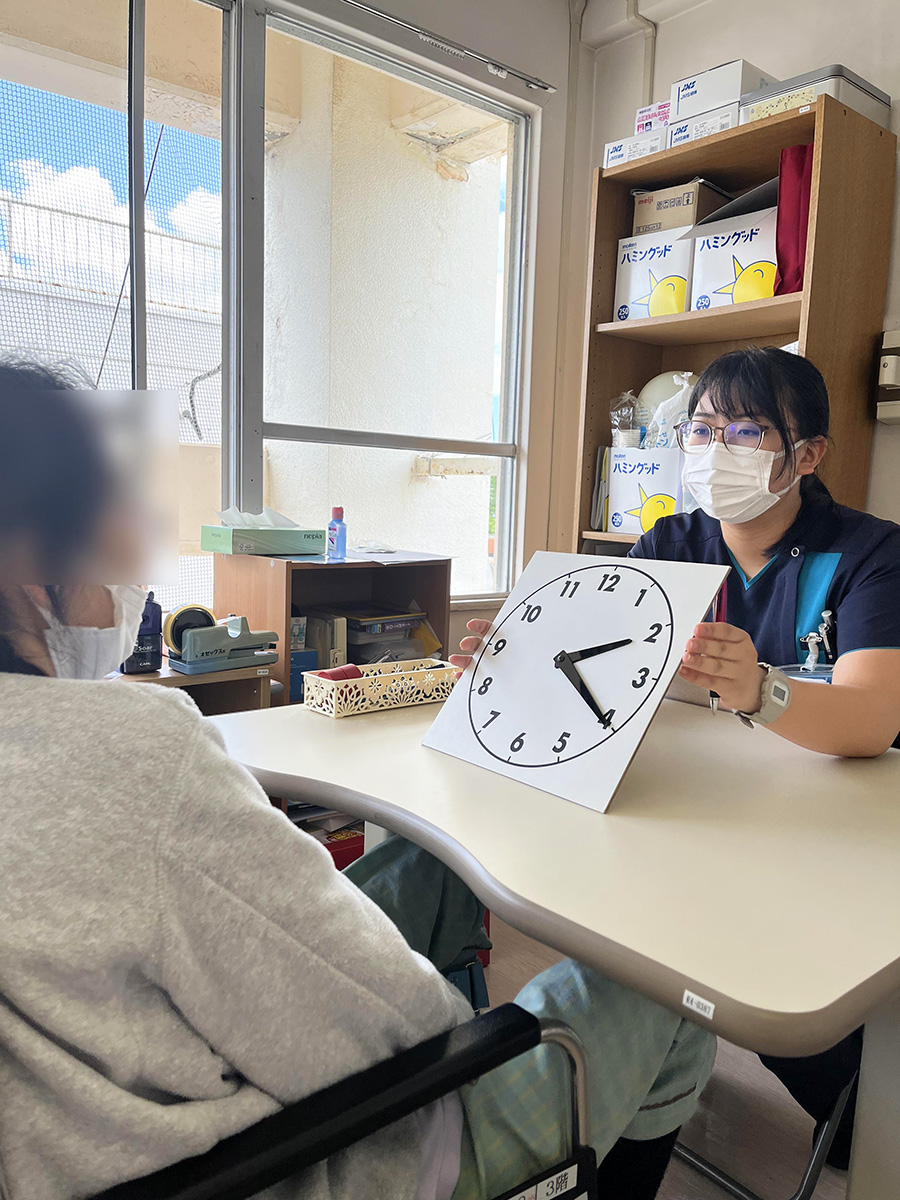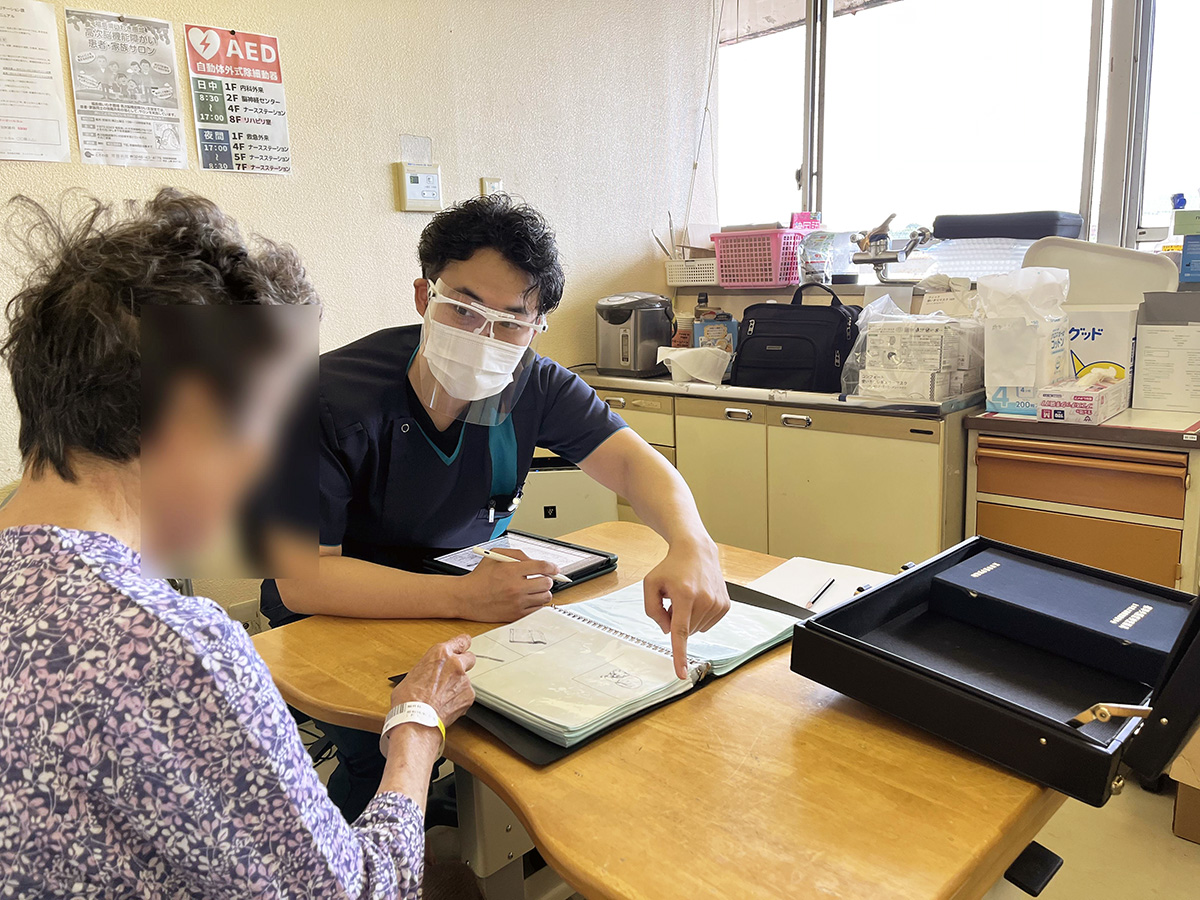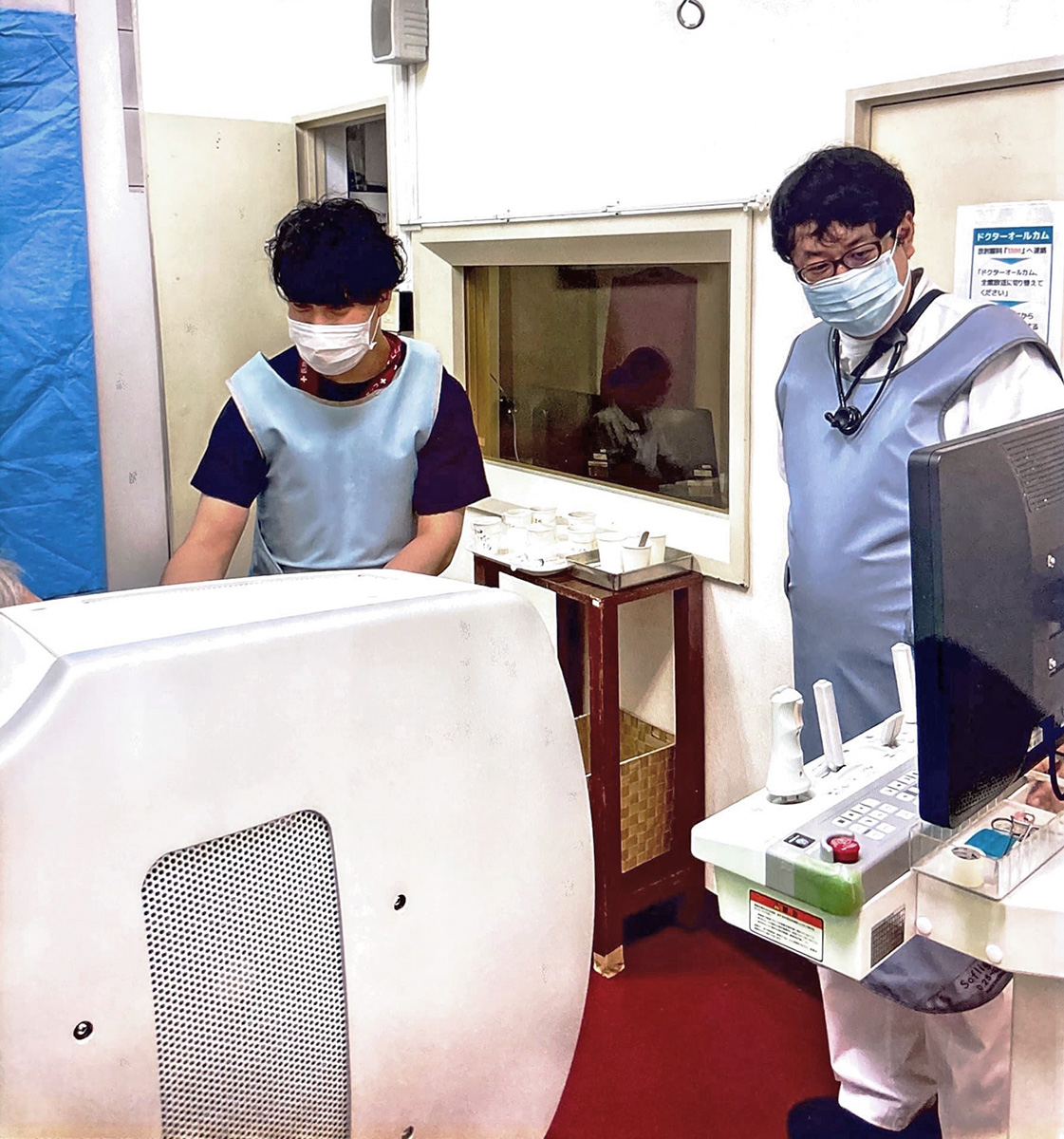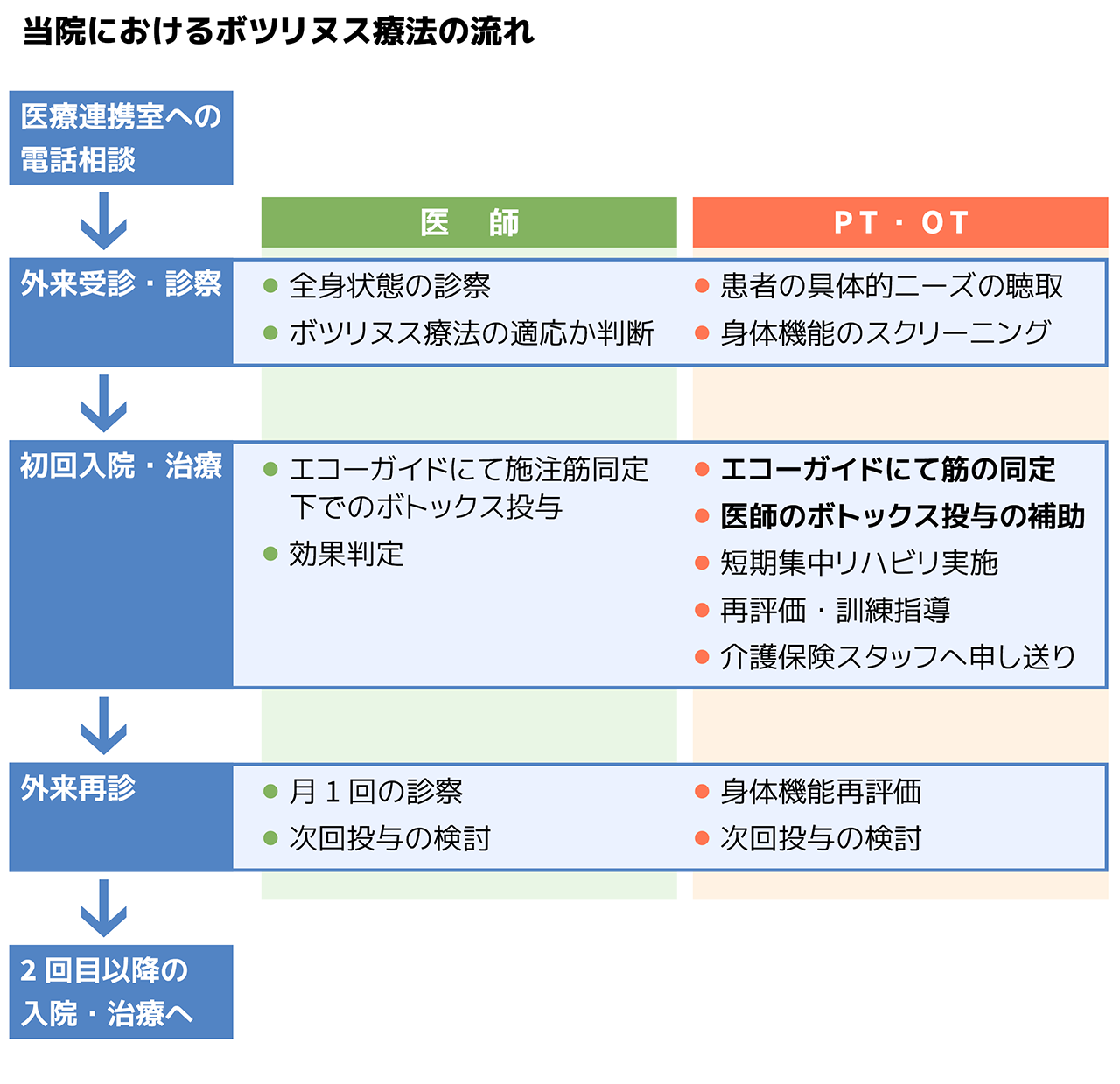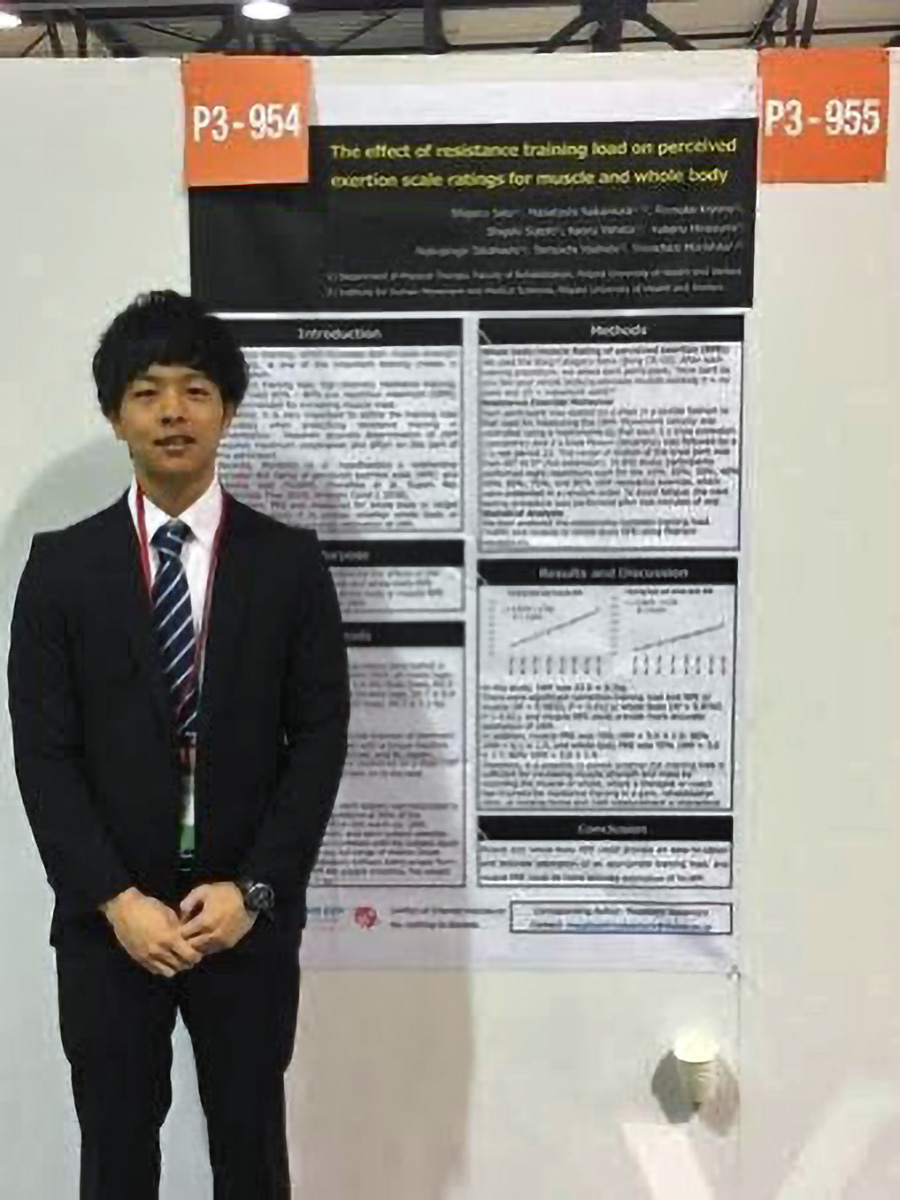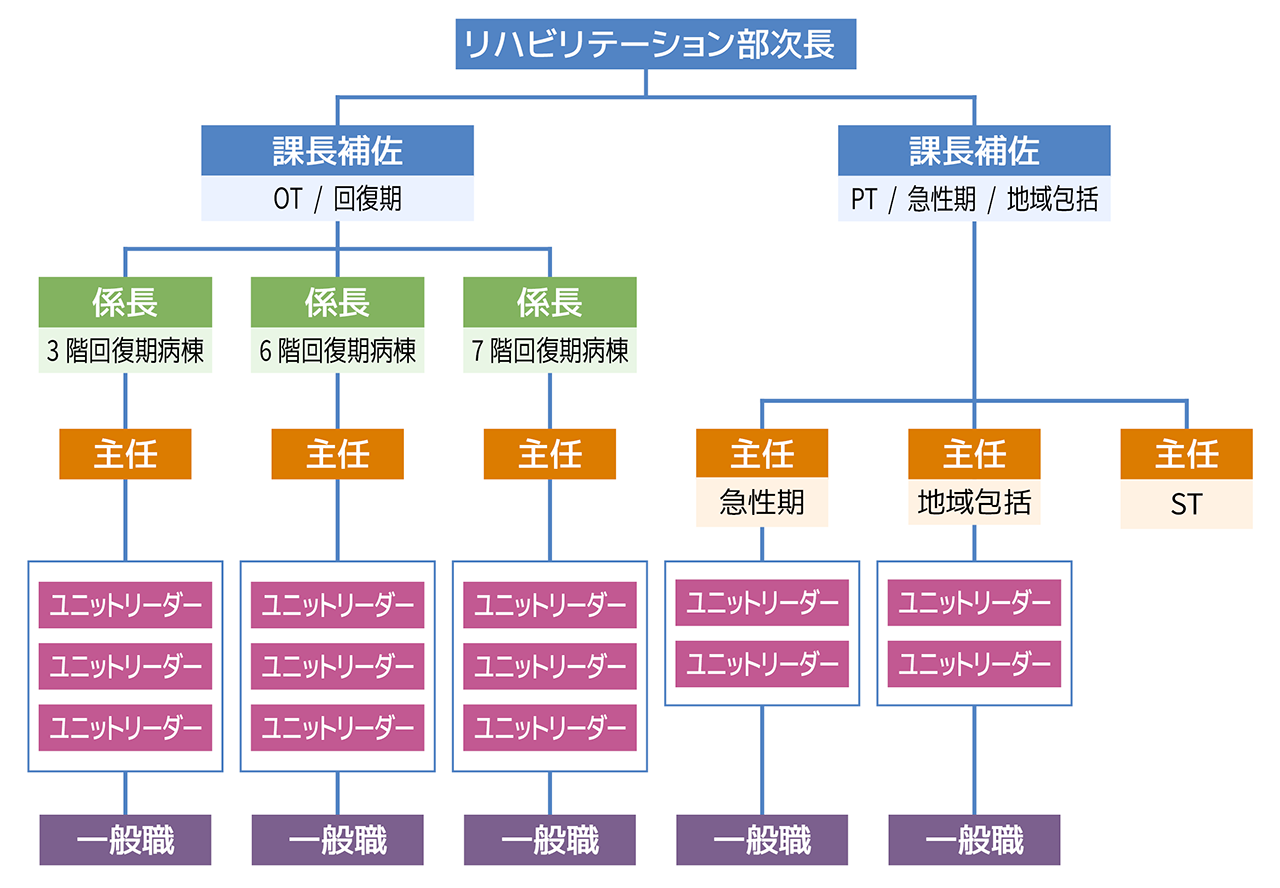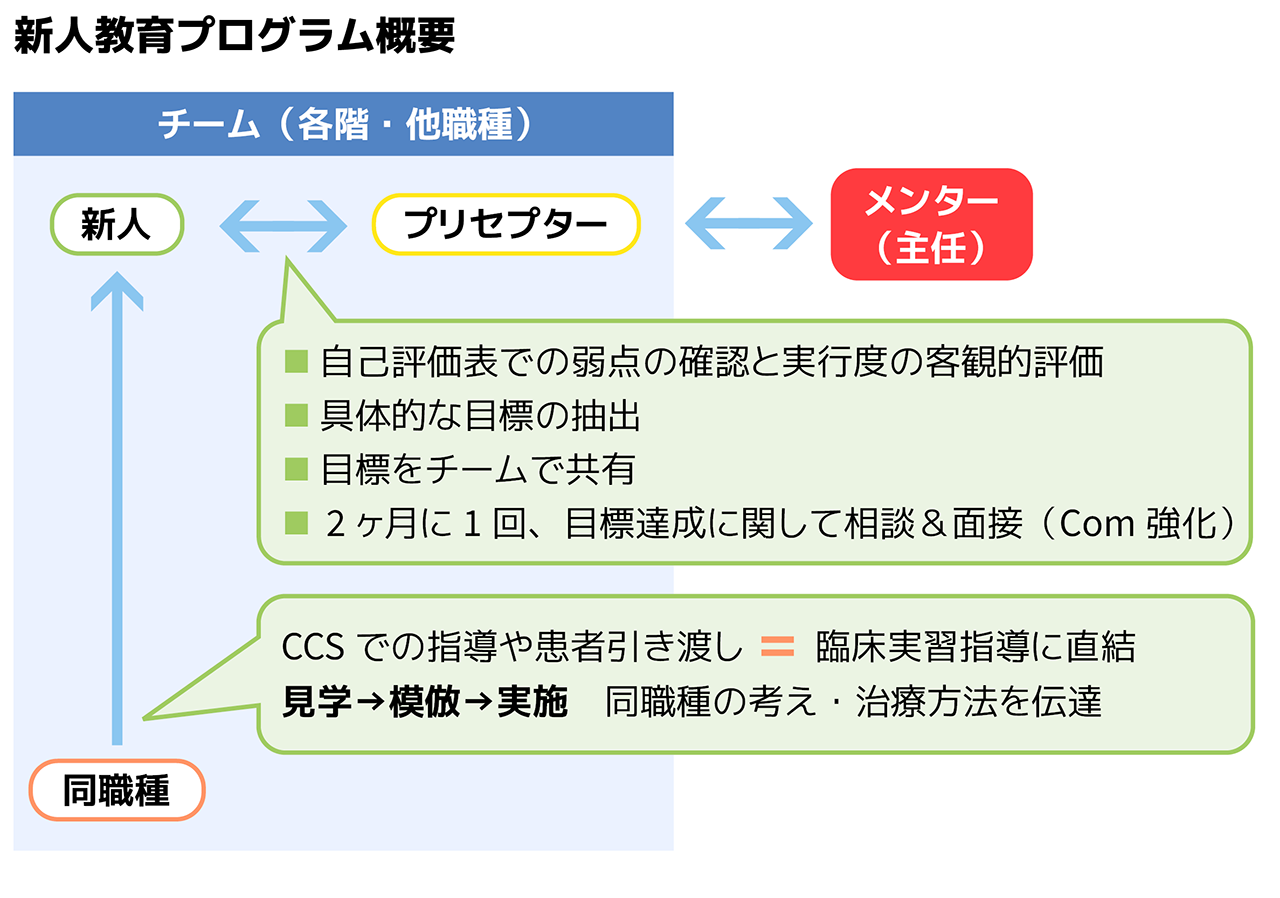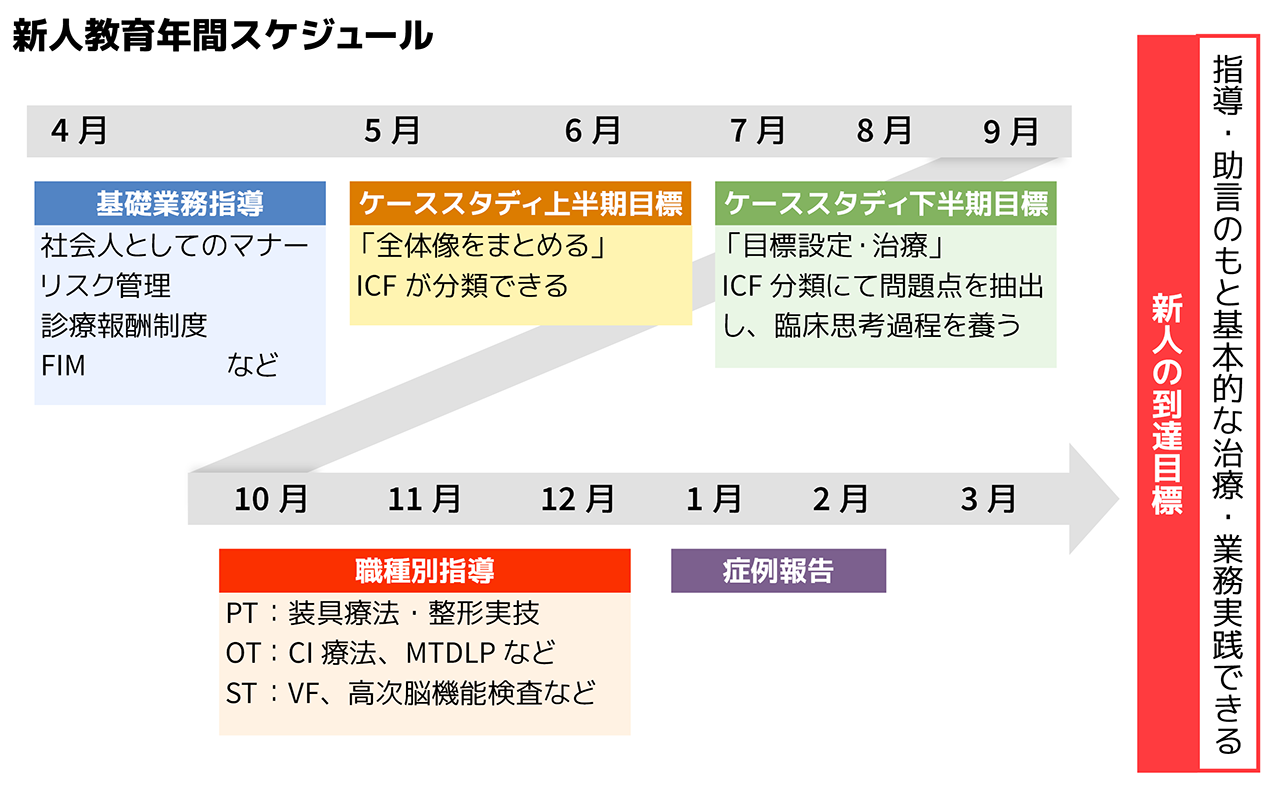��ʂ̕���
���n�r���e�[�V�����Ƃ�
�@���n�r���e�[�V�����Ƃ́A�P�ɋ@�\��}�邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�u�����炵�������邱�Ɓv��u�l�Ԃ炵�����邱�Ɓv���܂܂ꂽ�Ӗ�������A���̖ڕW�Ɍ��������ׂĂ̊����������܂��B
�@���n�r���e�[�V�����͈�t�A�Ō�t�A���w�Ö@�m�A��ƗÖ@�m�A���꒮�o�m�A�\�[�V�������[�J�[�A��t�A�Ǘ��h�{�m���������Ŋ��҂��܂̎��ÂɍőP��s�����܂��B
���@���n�r���e�[�V�����̃R���Z�v�g
�a�C�̔��ǂ���ݑ�ֈ�т�����Â��
�ݑ�A��ڎw��
�@���@�̃��n�r���e�[�V�����R���Z�v�g�Ƃ��ẮA�a�C�̔��ǂ���ݑ�Ő�������܂ŁA��т�����Â���邱�Ƃł���A�\�͂��ő�������A�ݑ�A��ڎw���Ă������Ƃł��B
���w�Ö@�Ƃ�
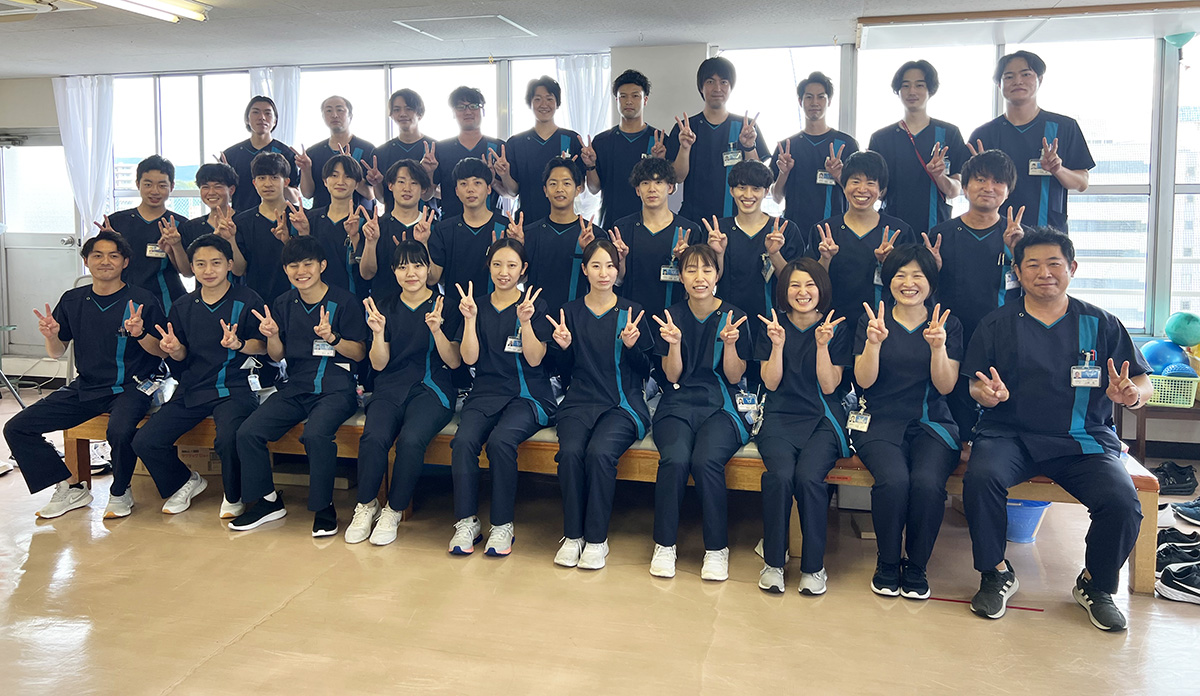
�@�g�̂ɏႪ���̂���l�ɑ��āA����A���A�����Ȃǂ̊�{����\�͂̉�A�Ⴊ���̗\�h��ړI�ɁA�^���Ö@�╨���Ö@����p���āA�����������퐶���������悤�Ɏx�����邱�ƁB

�߉���P��

�K�i���~

���s�P��
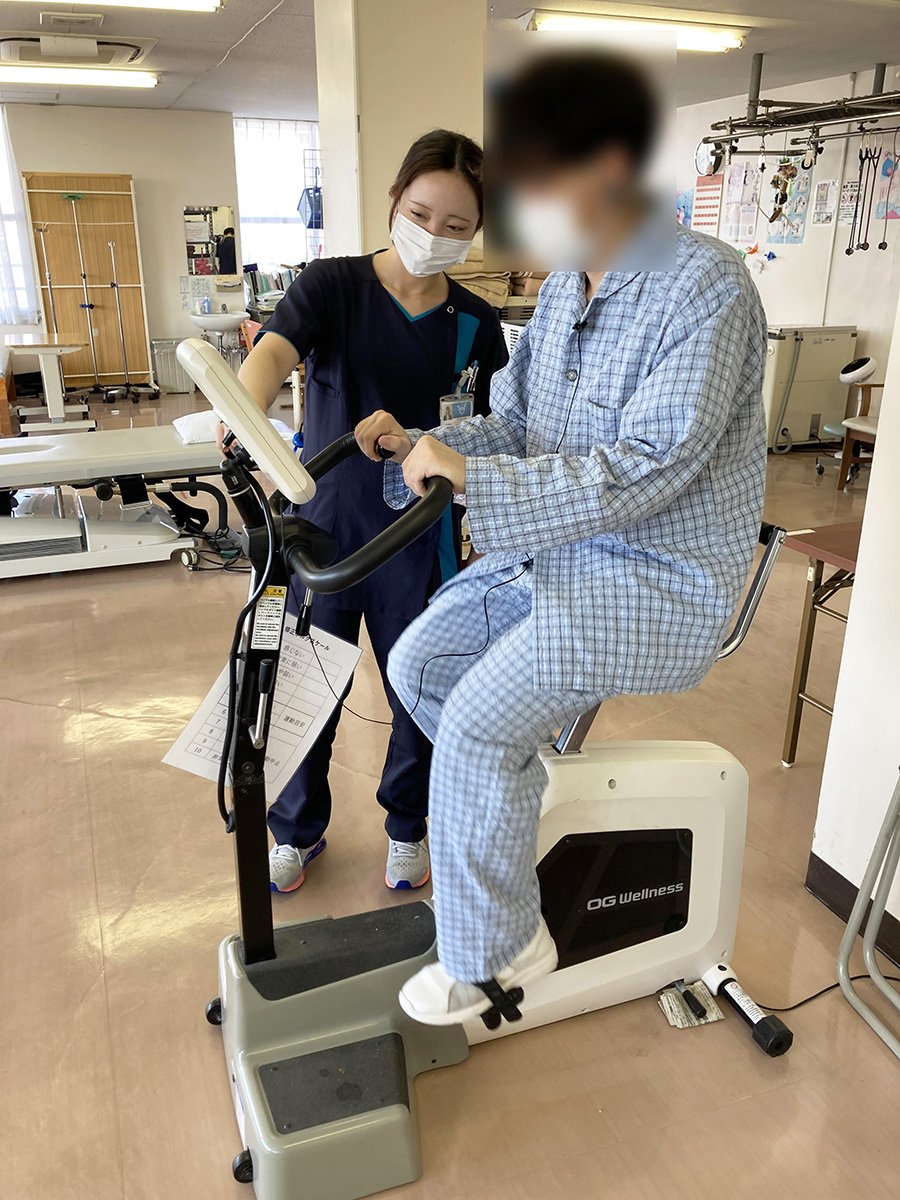
���]�ԃG���S���[�^�[
��ƗÖ@�Ƃ�

�@�S�g�ɏႪ�����A���퐶���𑗂��Ŏx�����K�v�ȕ��ɑ��č�ƁE������ʂ��Ă��̐l�炵�������������悤�Ƀ��n�r�����s���܂��B���E��ƘA�g����{����̊l���A�H���E���ʁE�X�߁E�g�C������Ȃǂ̓��퐶���ɕK�v�ȉ��p�\�́B�Ǝ���d���A��������A�Љ�ƂȂ��邽�߂̉��p�\�͂̊l����ڎw���܂��B

��w�I�k����
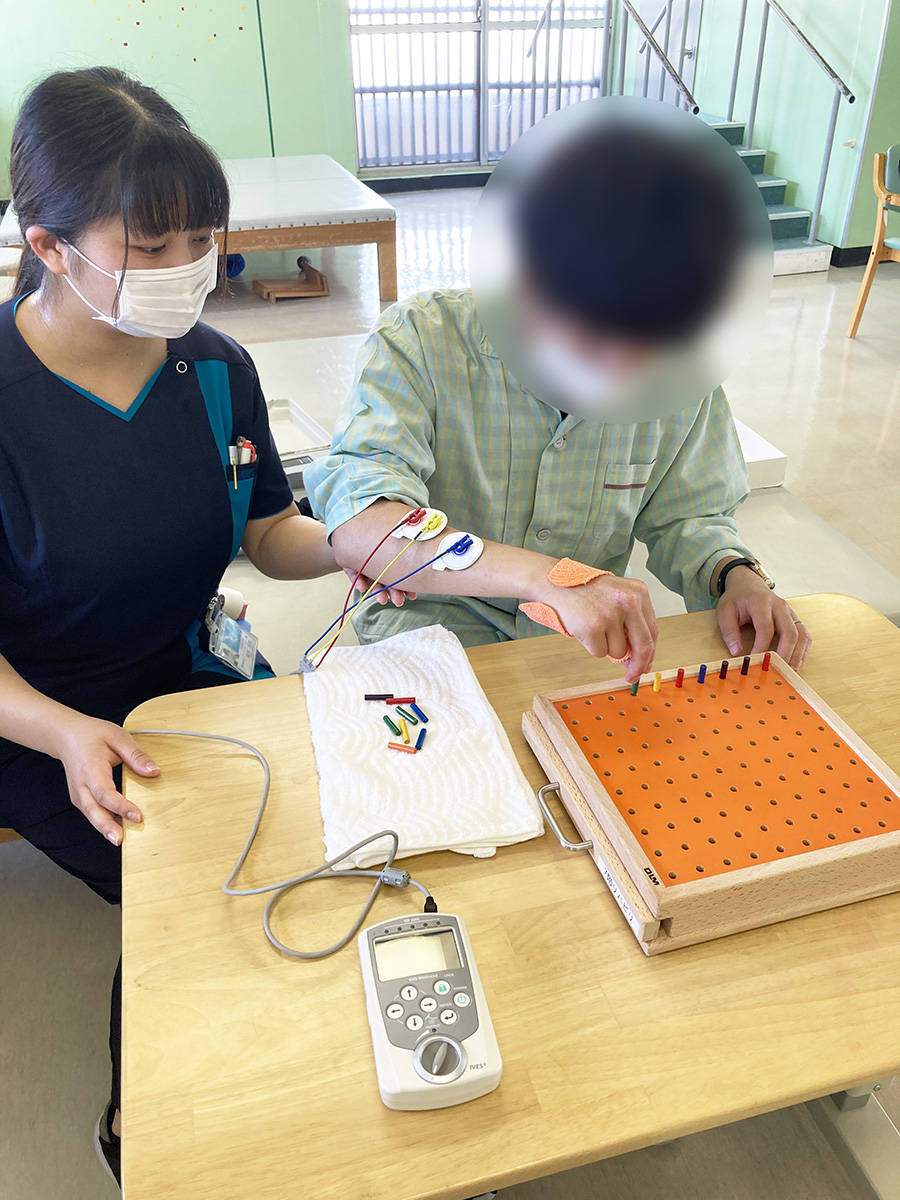
IVES�i���Ӊ^����^�d�C�h�����u�j
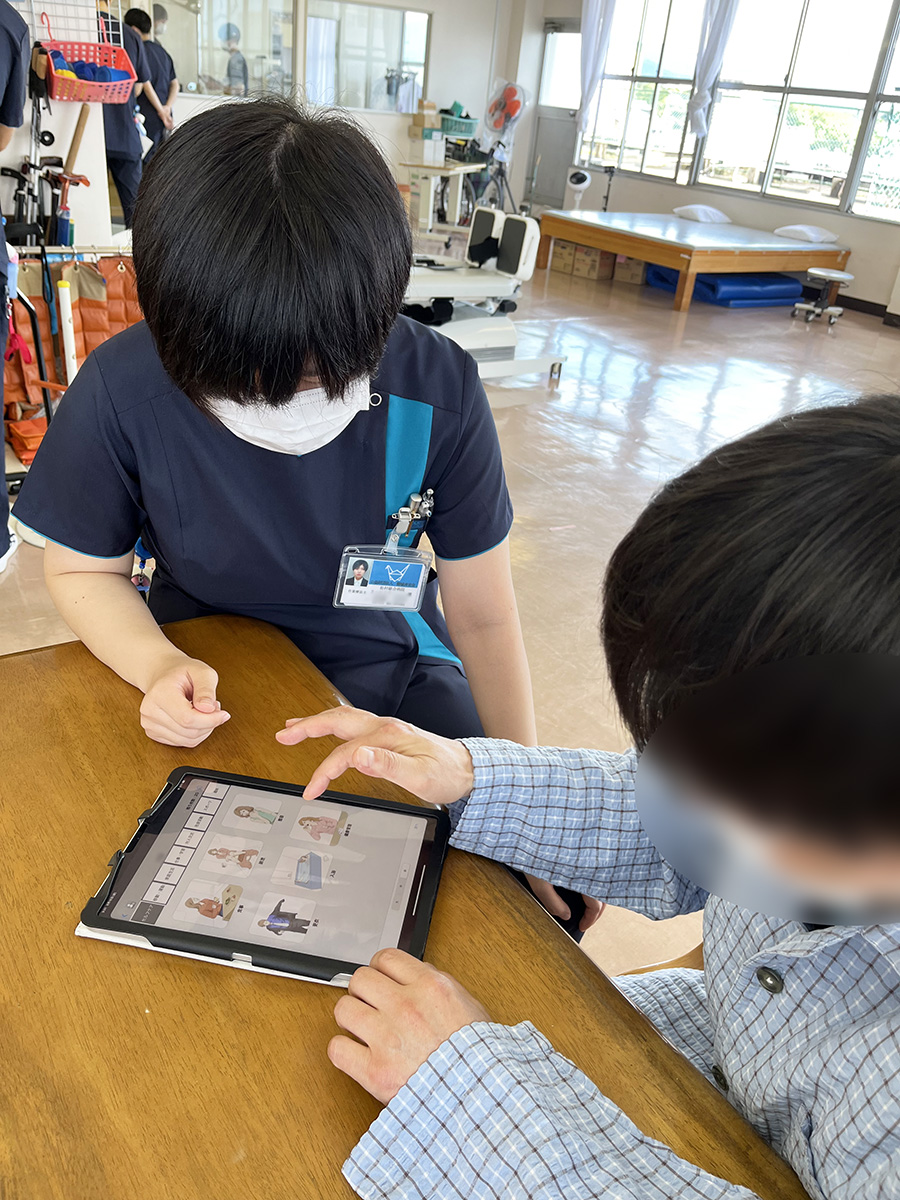
ADOC�i��ƑI���ӎv����x���\�t�g�j

�X�v�����g
���꒮�o�Ö@�Ƃ�

�@��Ƃ��Č���@�\�⒮�o�@�\���ቺ���R�~���j�P�[�V�����ɖ�肪����������ېH�E�����@�\�ɏႪ����������ɑ��A����̉A�\�͂̌���A�ێ���ړI�Ƃ��e�팟���A�]���A�P���A�w���y�щ������s�����Ƃ������܂��B
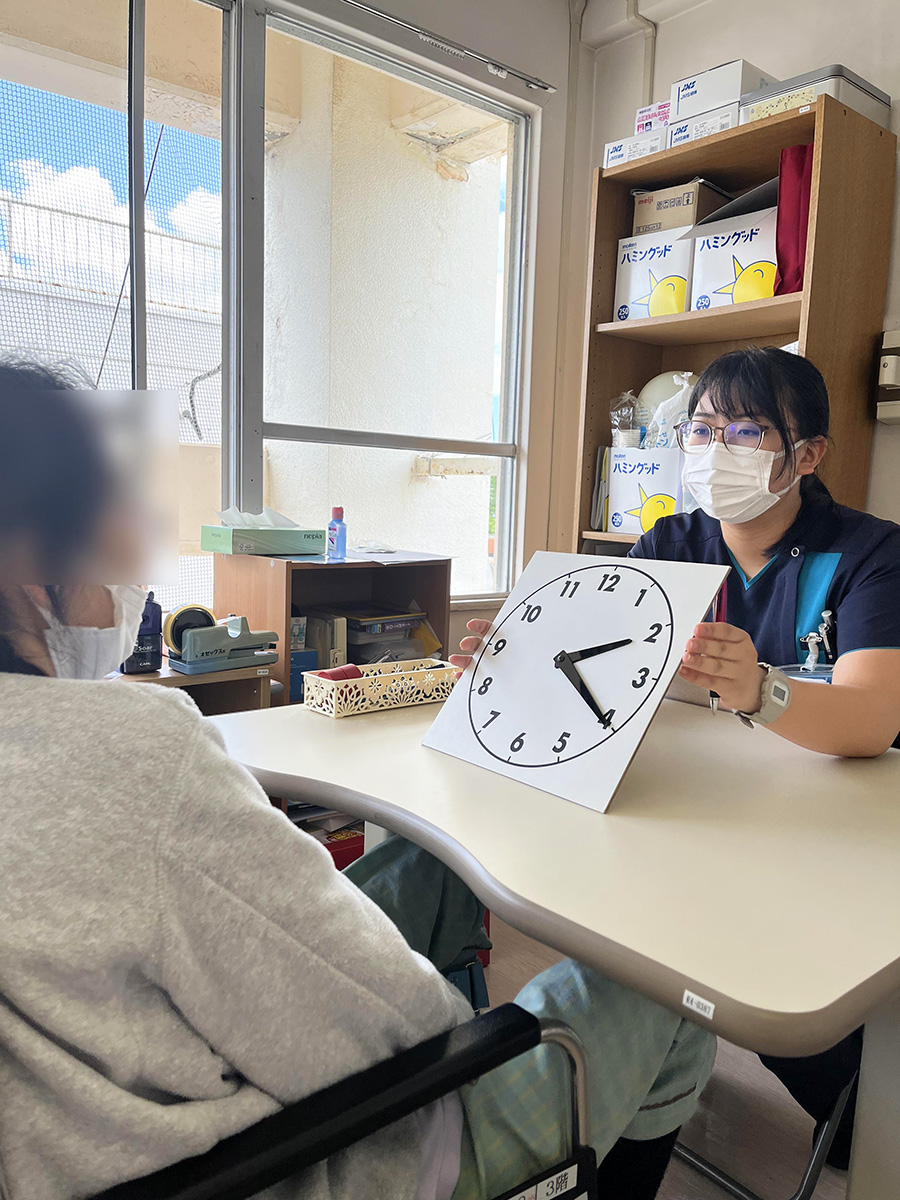
�����]�@�\�P��
�R�~���j�P�[�V������Q�@�]���E�P��
�@�R�~���j�P�[�V������Q�̏�Ԃ��ڂ����]�����A���җl�ɂ������P���v���O�����𗧂Ăĉ������܂��B
�@�މ@�Ɍ����ẮA�R�~���j�P�[�V�������@��ݑ�ł̏������s���܂��B
�����]�@�\��Q�@�]���A�P��
�@�L����Q�A���ӏ�Q�A���s�@�\��Q�A�Љ�I�s����Q�̕��ɕ]�����s���A�Љ�Q���Ɍ������P������܂��B
�ېH�E������Q�@�]���E�P��
�@���E��Ƌ��͂����S�ł���A���������A�����i�K�Ō�����H�ׂ��悤�ϋɓI�ɌP�������{���Ă��܂��B

���o�P��

�����P��
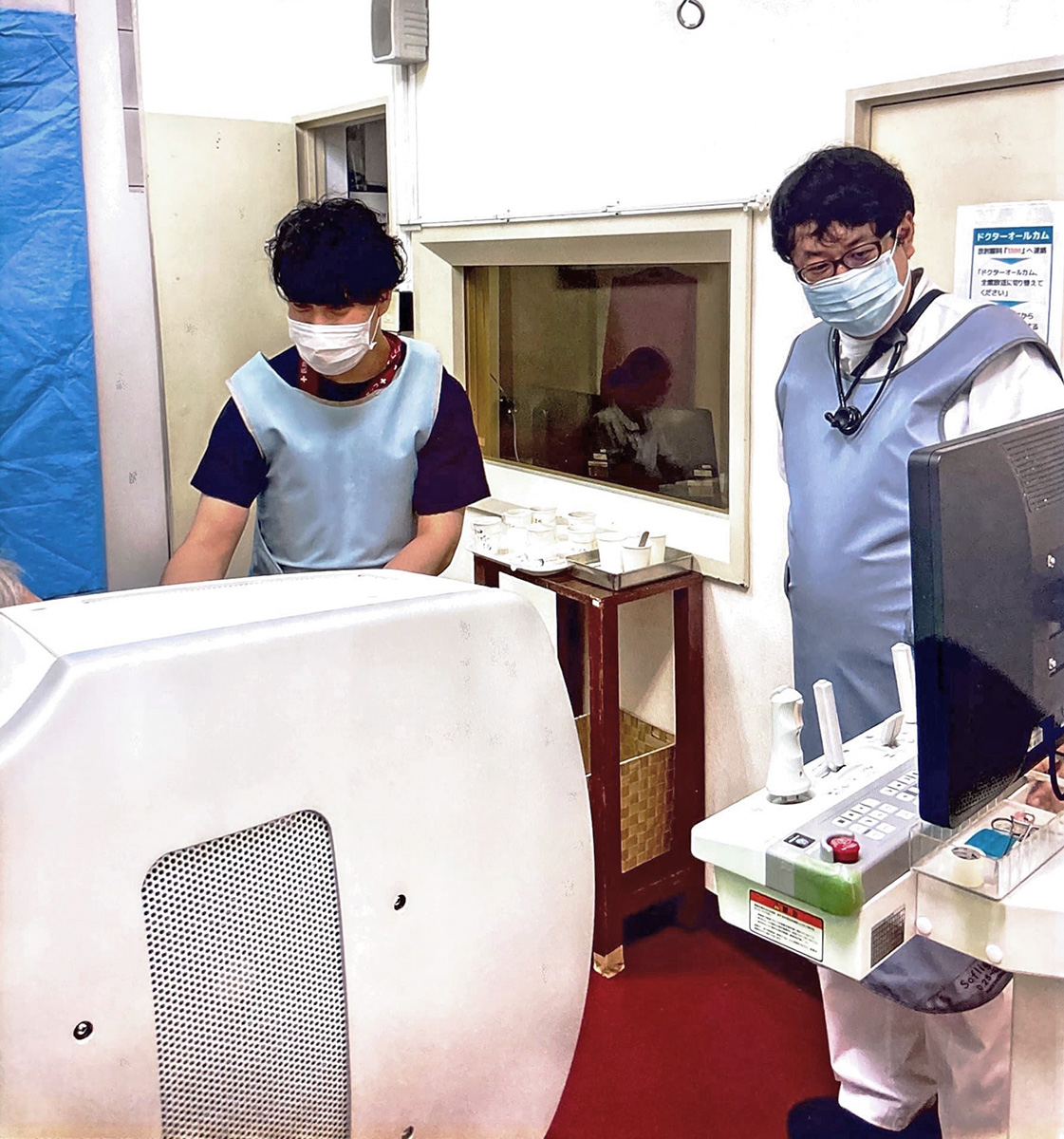
VF�i�������e�����j
���@�̓��F
�����n�r���e�[�V����
�@�a�����Ƀ��n�r������z�u���A�a���������Ń��n�r���������ł�����ݒ���s���Ă��܂��B

�@�\�P����

�����]�@�\�P����

���꒮�o��
�@�a���肵�n�߁A���ǂ���2�����ȓ��̊��҂���ɁA���܂��܂ȐE��̃X�^�b�t���@�g�Q������̖h�~�ƎЉ�A�h�@��ڕW�Ƃ������n�r���e�[�V�������W���I�ɍs���a���ł��B
�@��]�̃��n�r���e�[�V�����X�^�b�t���a���ɓ���A���҂���̏�ԂƑމ@��̐��������l�������P�����s�Ȃ��܂��B
�@�]�������n�r���e�[�V�����F��Ō�t�ƘA�g��}��A�H���E���e�E�r���E�X�߁E�����Ȃǂ̓��퐶�����삪�������Ɋ�Â������̂ɂȂ�悤�ɁA�a�������̒��Ŋ��҂���₲�Ƒ��ƈꏏ�ɂȂ��čl���Ȃ���A�v���[�`���s�Ȃ��܂��B
�Ƒ��w���i��@�j
�@�ݑ�ɖ߂邽�߂ɉƑ��̋��͂��K�v�Ȃ̂ŁA�Ƒ��w�������{���Ă���܂��B
�Ɖ��K�⒲��
�@�ݑ�Ő����ł��邩�H �������͕K�v���H �Ƃ������A�h�o�C�X�����邽�߂ɁA�ݑ�ɖK�₵���ۂɔ\�͂Ɗ����Ƃ炵���킹�m�F���܂��B
�`�[���Љ�
�{�c���k�X���Ã`�[��

�@�{�c���k�X���ẤA�z�k�i�������キ�j�ɂ��߉���̐�����؋ْ��ُ�̉��P�Ɍ��ʂ�����܂��B�܂��A���^��̒Z���W�����n�r���⎩��P���̒ɂ��A���җl�̐����̉��P��ڎw���܂��B
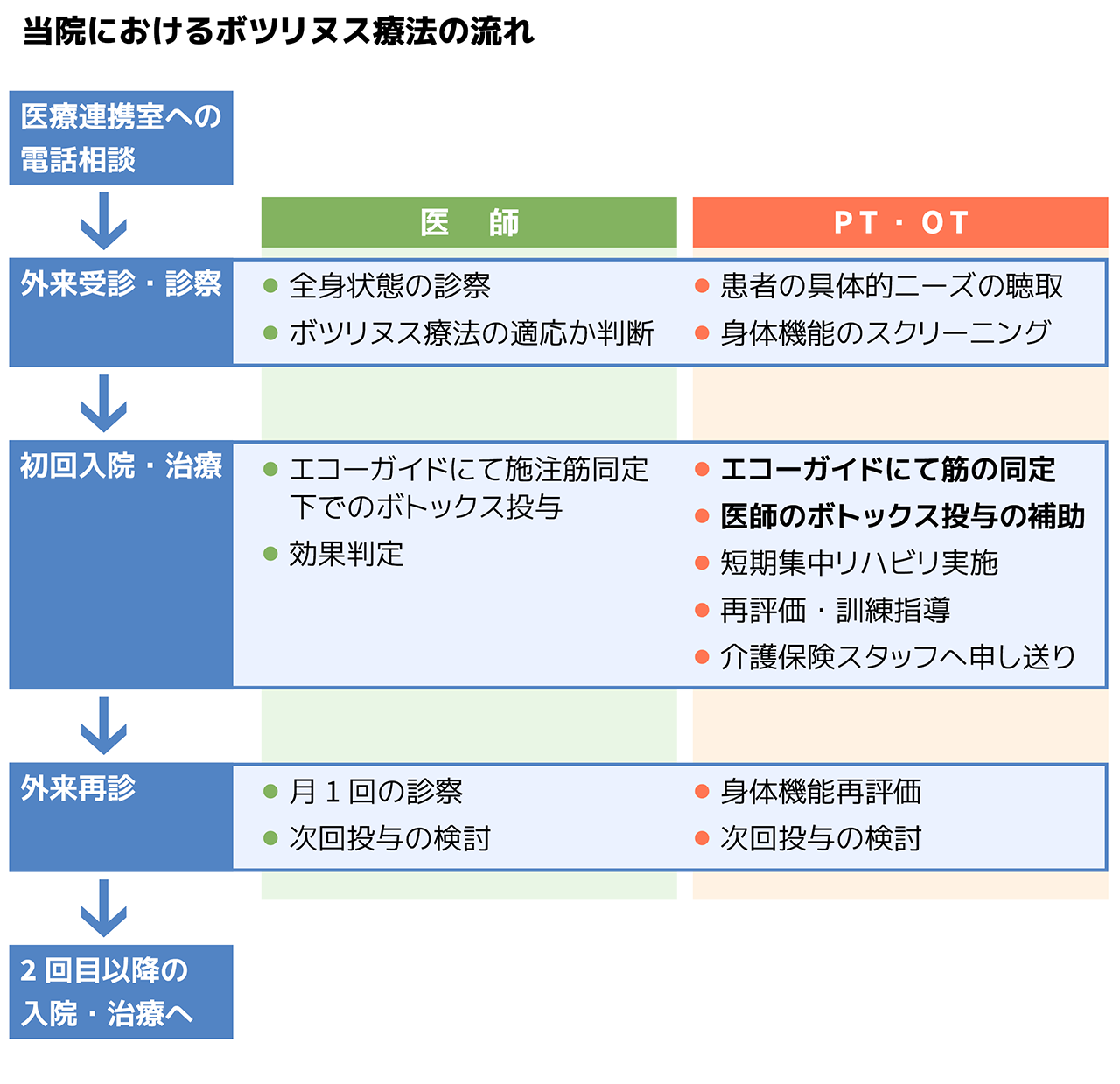

�{���̗l�q
����`�[��

�@���@�̃��n�r���ł́A�d�x�Ж���҂ɑ��Ē�����������g�p���A�����ɗ��ʁA���s���K�����{���Ď��Âɑ����ϋɓI�Ɋ��p���Ă��܂��B���җl�ɍœK�ɑ����o����悤�Ƀ��n�r���X�^�b�t�����ő���J���t�@�����X�����{���܂��B�g�̓I�ȕ]����Љ�I�ȏ���łȂ��]�摜��ؓd�}�����p���q�ϓI�ȃf�[�^����������̓K���f���܂��B�ʏ풷��������͑���[���ɖ�3����4�T�ԗv���܂����A���@�ł͉摜�g���[�X�ɂ�钷��������̌^��������Ă����10���ԂŔ[�i���邱�Ƃ��o���܂��B
�����`�[��
�@�����`�[���ł́A�u�������ʂ�Տ�����ɊҌ�����v�����b�g�[�Ƃ��A���X�������s���Ă��܂��B��ɔ]������Ж���҂�ΏۂɁA�^���Ö@���Ö@�A�d�C�h���Ö@�̌��ʂ�2�����摜��͂�ؓd�v��p���Č����Ă��܂��B
�@���݂͑��{�݂Ƌ������A�]������d�x�Ж���҂�Ώۂɒ�����������g�p�������s�g���[�j���O�����s�̉�݉@���Ԃɋy�ڂ��e���������Ă��܂��B���X�̊����ł́A����I�ɕ�����J�Â��A�����A�C�f�A�̔��Ă⌤�����e�̃f�B�X�J�b�V�����A���v��@�̕������s���Ă��܂��B�����āA�������e��ϋɓI�ɊO�����M���Ă���A�w��\��_�����M�E���e�ɐs�͂��Ă��܂��B
�@�ȏ�̊�����ʂ��āA���X�̗Տ��Ŋ�����^����������A���җl�Ɏ��̍�����Â�ł���悤�ɓw�߂Ă��܂��B
�����Ɋւ��邲���͂̂��肢
�����Ɋւ��邲���͂̂��肢�yPDF�z
��Ï]���҂̕���
2023�N�x���n�r���e�[�V�����ۖڕW
- �@�K��n�r���̕���̐ݗ�����
- �A�a�@�@�\�]���X�V��R�Ɍ��������n�r���Ɩ��̌������ƃ}�j���A���쐬
- �B�ċz���n�r���`�[���̐ݗ�
- �C1�l1�l�����Y�����l�������Z���t�}�l�W�����g�̎��H
�g�D�}
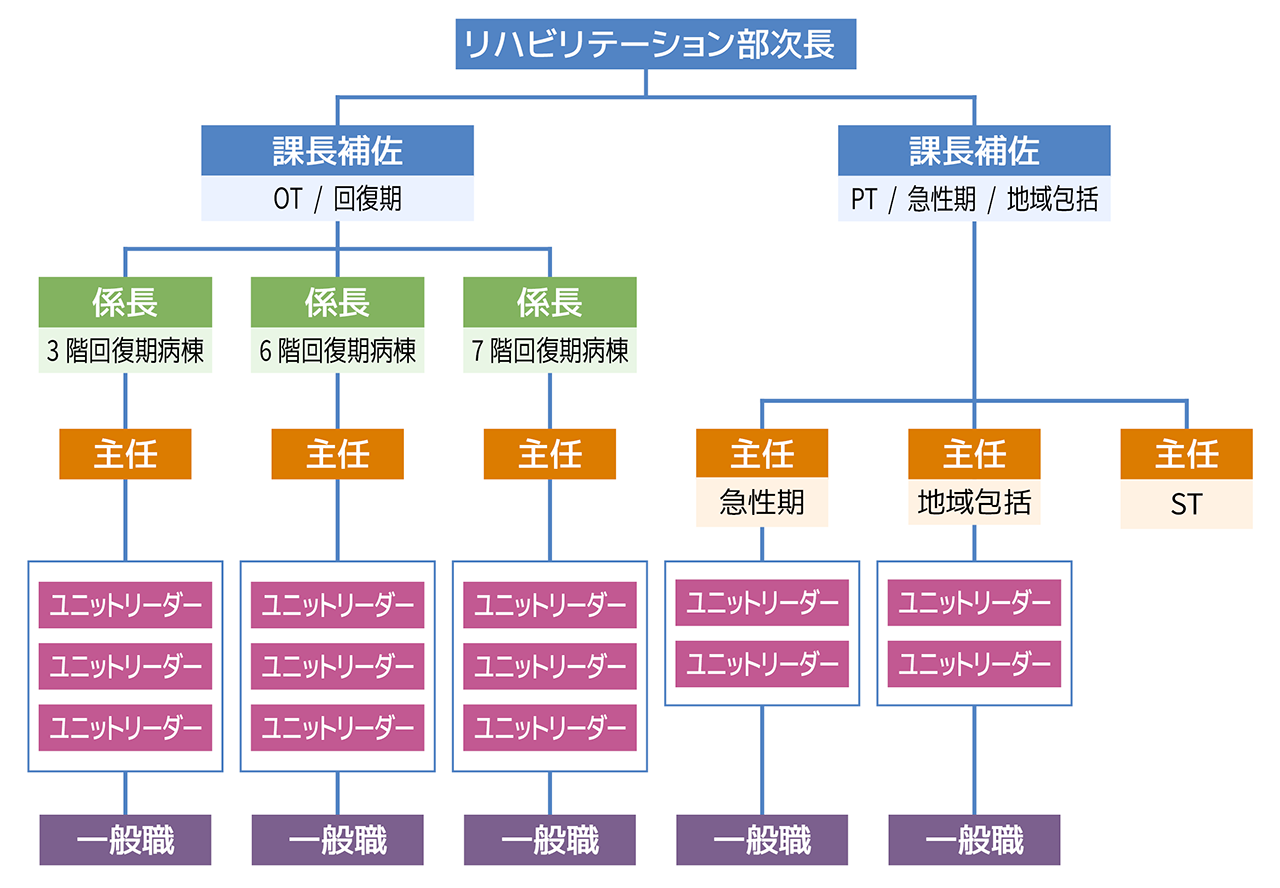
�X�^�b�t�l���i2024�N11�����݁j
|
| PT | 39�� |
| OT | 18�� |
| ST | 8�� |
| ���� | 1�� |
| ���v | 65�� |
���i�擾�Ґ��i2024�N11�����݁j
|
| �F�藝�w�Ö@�m |
11�� |
�i�Ǘ��E�^�c�j�R��i�A��c�N��
�i�]�����j����B��A�g�c���l�A�n糏r��A
�����E���A�����m���A���J��a�M�A���D�A
���Əx�A�����͖� |
| 3�w����ċz�Ö@�F��m |
8�� |
�R��i�A��c�N���A�R���R�G�A�n糏r��A�g�c���l�A�����b���A���J��a�M |
| ���x������ |
2�� |
��؍N�V�A����B�� |
��ƗÖ@�m�Տ��w����
�u�K��b�l |
1�� |
�V�ȗS�� |
| �a�@�o�c�Ǘ��m |
1�� |
�R��i |
���K���������
|
PT |
OT |
ST |
| �Տ����K�w���� |
21�l |
9�l |
- |
| 2023�N�x�@���K�� |
10�l |
5�l |
0�l |
| 2022�N�x�@���K�� |
10�l |
10�l |
1�l |
| 2021�N�x�@���K�� |
10�l |
5�l |
0�l |
| 2020�N�x�@���K�� |
1�l |
0�l |
0�l |
�V�l����v���O����
�@���@�ł͐V�l����v���O�����̈�Ƃ��ăP�[�X�X�^�f�B��������A�N�Ԃ�ʂ��V�l���x������g�݂����{���Ă��܂��B
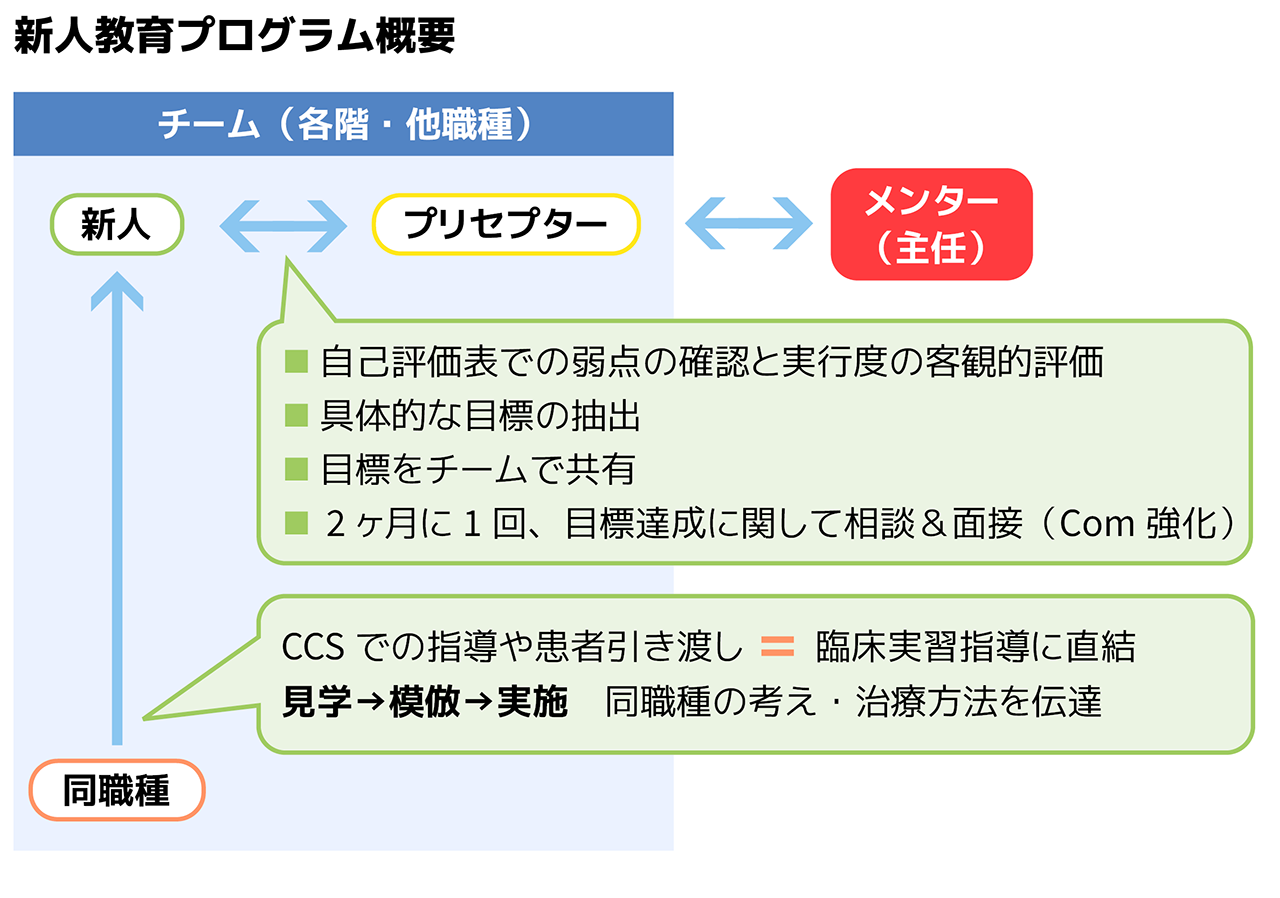
�@�V�l�̓��B�ڕW�Ƃ��āu�w���E�����̉��A��{�I�Ȏ��ÁE�Ɩ������H�o����v�u�P�[�X�X�^�f�B��ʂ��Đ�y�̍l�����⑼�E��̘A�g���w�їՏ��v�l�ߒ���{���v���f���A�N�ԃX�P�W���[�����\�z���Ă��܂��B
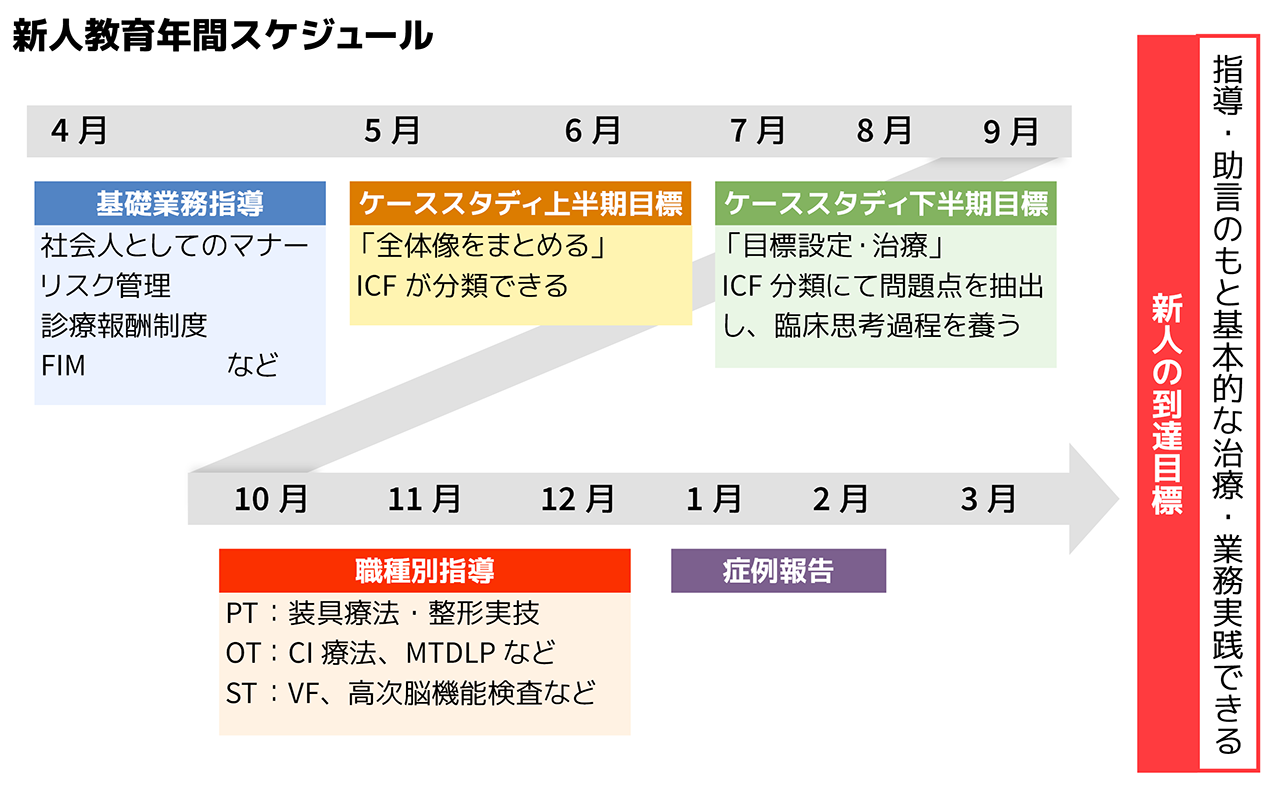
�@�O����
���\
2023�N�x
��34������ƗÖ@�w��
- ���숻�q
- �w���@�ł̃��N���G�[�V�����̎��g�݁x
MTDLP���ጟ����
- �n�ӖG�X
- �wMTDLP�����p�������ƂŎ��Ȍ��͊������サ�މ@���������i�n�슈���E�����j�̌p���Ɍ��т�������x
- �g�c����
- �w�㎈�ɏœ_������MTDLP��W�J��������x
��33��@���k��ƗÖ@�w��
- �V�ȗS��
- �w���ߏ�Q�ɂ�����ۑ�u���^�A�v���[�`�̊ւ�x
�ߘa5�N�x�@���킫�x���{�ݑ�\�Ҍ��C��
- �R��i
- �w���U�w�K���x�ɂ��āx
��21��@���{�_�o���w�Ö@�w��
- �����E��
- �w���@���a���ł̔]�����Ж���҂ɂ����钷��������쐻�����̒Z�k���A���s�\�͂ƍ݉@���Ԃɋy�ڂ��e���x
- �����m��
- �w���s���̃N���A�����X�ቺ�ɑ��đ��p�I�ȃA�v���[�`���t������1�Ǘ�x
��22�������w�Ö@�m��w�p�W��
- ���J��a�M
- �w���l�]������҂ɑ����z�k���Á@�`�{�c���k�X���Á`�I�[�_�[���C�h�Ԉ֎q�쐻�܂Ł`�x
- �n��D��
- �wLateropulsion�y�ю��o�I���������ʂ̕Θ߂�悵���Ǘ�ɑ��Ċ��o�t�B�[�h�o�b�N��p����1�Ǘ�x
��99���ֈ�w��
- ��؍N�V
- �w�ǐՒ����̌��ʂɂ��ā@�`���@����މ@�������ւ̃A���P�[�g�����̌��ʂ���`�x
- �n糏r��
- �w���n�r���e�[�V�����ۂɂ�����V�l����̎��g�݁x
��28����{��b���w�Ö@�w��w�p���
- ������
- �w�ؗ͑�������ыؔ����ʂ����߂邽�߂̃��W�X�^���X�g���[�j���O�����@�`�߉���Ƌ؎��k�l���ɒ��ڂ����헪�`�x
���킫�x���Ȃ�ł�����
- ���v�ԊC�l
- �w�]�����Ж���҂ɑ�����s�P���@�`�Z��������𒆐S�Ɂ`�x
��41�k���w�Ö@�w�p���
- ���J��a�M
- �w�A�ӂ��B���Ȕ]�����Ж���҈�Ǘ�ɑ���r���R���g���[���l���܂ł̎��g�݁x
��10����{�{�c���k�X���Êw��w�p���
- ����E��
- �w�{�c���k�X���Ê��҂ɑ��铖�@�̒n��A�g�ɂ��ă{�c���k�X���Ãm�[�g�̊��p�x
���킫�z�k����Web�Z�~�i�[
- ������
���J��a�M - �w��Ⴢ̌��ǂ̕��Ɋ��߂Ă݂܂��H�@�`���s����A����ω����鎡�Â̒�ā`�x
2022�N�x
���킫�x���Ȃ�ł�����
- �����E��
�����m�� - �w���@�̒���������쐻�Ɍ��������g�݂Ɗ��p�@�ɂ��āx
��21�������w�Ö@�m�w�p�W��
- ���J��a�M
- �w���o��Q����ѐg�̎��F��悷��]�����Ж�Ⴢɑ��Ē�����������g�p���A�����ƕ������Ɏ�������Ǘ�x
- ���D
- �w�]�����Ж�҂ɑ��鑕��Ö@�ɖ����d�C�h�������������Ƃŗ������s�l���ł����Ǘ�x
- ����E��
- �w�]�����Ж���҂ɂ����钷���I�ȃ{�c���k�X�Ö@�̌o�߂ƌp���I�ȃ��n�r���e�[�V�����̕K�v���ɂ��āx
RESEARCH TO PRACTICE 2022
- ������
- �weffect of daily 3-5 maximum voluntary isometric on elbow flexor strength�x
��27����{��b���w�Ö@�w��
- ������
- �w�ؐL���ʂɂ����郌�W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ�������Ɣ������ɂ�����ؗ͑����̊֘A���̌����x
�z�k���Á@���킫web�Z�~�i�[
- ������
- �w���@�̃{�c���k�X�Ö@�̗���Ə㎈�z�k�ɑ���n��A�g�x
- �V�ȗS��
- �w�㎈�z�k�ɑ���{�c���k�X�Ö@�̎��g�݂ƒn��A�g�̏d�v���x
���k�x����ƗÖ@���C��
- �V�ȗS��
- �w�����n�r���e�[�V�����a���ł�MTDLP�̊��p���@�Ɠ��@�̎��g�݁x
��ƗÖ@�m�Տ����K�w���ҍu�K��
- �V�ȗS��
- �w�Տ����K�w�����@�_�A�����s����}�l�W�����g�����p�����Տ����K�̎w�����@�x
- �V�ȗS��
- �wMTDLP�ɂ��}�l�W�����g�ߒ��̎��H�x
��32�k��ƗÖ@�w��
- ������
- �w�������]�������҂�ADOC�ɂ��ڕW�ݒ�Ŗ��̎g�p�s�������P��������x
- ���{���@
- �w�����n�r���e�[�V�����a���ɂ����镪�}����a�iBAD�j��悵���d�x�㎈��Ǘ�ɑ��镡���Ö@�̌��ʁx
MTDLP���ጟ����
- ���{���@
- �w���n�r���S�ʂɎI�ł������Ǘ�ɑ��Ė�ბ��㎈�ɑ���MTDLP���g�p���O�����Ȏv�l�s���ւƎ�e�����Ǘ�x
- ����T��
- �wMTDLP�̎g�p�ɂĖڕW�����m������A�މ@��̐����ɖڂ�������ꂽ����x
- �����D��
- �w���M�����������x�Ж����MTDLP�������������ƂŁu���M�v�����߂��A���������ł���E�ꕜ�A���\�ɂ�����Ǘ�x
- ����O�K
- �w�����ˑ��x�����ǗႪ���g�ōs������܂Łx
2021�N�x
���킫�x���Ȃ�ł�����
- �R��i
- �w�V���U�w�K���x�ɂ��āx
���킫�x���Ǘᔭ�\��
- ��ؒq��
- �w�]�[�ǔ��nj�d�x�E�Ж�Ⴢ�悵���Ǘ�ɑ��A���@�}�����ł̎��g�� �`photo trace �g�p�`�x
- ����\��
- �wphoto trace�ɂ�钷����������쐻���������s�P������80��㔼�j���x
��26����{��b���w�Ö@�w�p���
- ������
- �w�قȂ�ߊp�x�ɂ�����Б��̓��������W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ��ؔ��E�ؗ͑��������cross-education�̔�r�x
�������
- �����E��
�����m�� - �w���×p����������̃f�W�^���v�̎g�p�o���x
��21��V��������w��w�p�W��
- ������
- �w�قȂ�؎��k�l���ɂ�����3�b�Ԃ̍ő���k���ؗ͂ɋy�ڂ��e���̔�r�x
��2����{�����Ö@������w�p���
- ������
- �w�قȂ�؎��k�l���̃��W�X�^���X�g���[�j���O�ɂ��ؔ�储��ыؗ͑����̔�r�x
��32������ƗÖ@�w��
- �����]����
- �w�މ@��̖ڕW���o�ɐ����s����}�l�W�����g�����p���A�ƒ�������̍Ċl����
����������x
- ���X�؉荁
- �w�������ɂ��C�����E����l���Ɏ������p�[�L���\���a���҂�1��x
- �����D��
- �w�E������Ԗ������҂ɑ���g�C������A�v���[�`�x
�S����ƗÖ@�w��
- �V�ȗS��
- �w�{�c���k�X�Ö@�Ώێ҂֏C��CI�Ö@�̌��ʌ��x
2020�N�x
���k��ƗÖ@�w��
- �V�ȗS��
- �w���@�ł̃{�c���k�X�Ö@�̗���ƍ���̓W�]�x
- ���c�m�u
- �w�ނ�̎d�|�����ł���悤�ɂȂ�ƈӖ��̂����Ƃ�ʂ��Ė����̍Ċl�����ł�����Ǘ�x
�n��K��n�r��������
- �����m���E
���J��a�M - �w����̒n��A�g�x
���킫�x���V�l�Ǘጟ����
- �����W��
- �w����̍đI��A�^���Ö@���s�����s�@�\�����P�����������]�����Ǘ�x
- ���ˉċP
- �w�Ґ��[�NJ��҂ɑ����s�⏕�p���i�K�I�ɕύX�����s�P�������{�����Ǘ�x
�_���f��
���������w�Ö@�w
- �����m��
- �w�����������Z��������ւ̃J�b�g�_�E����i�K�I�ɍH�v�����Ǘ�x